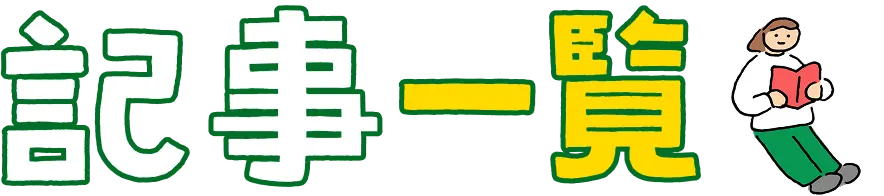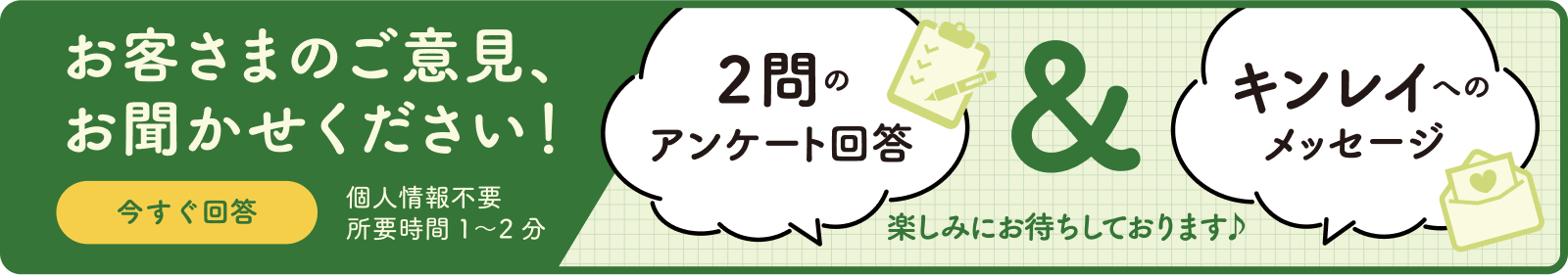問い続けるのは、
誰にとってのおいしさか?
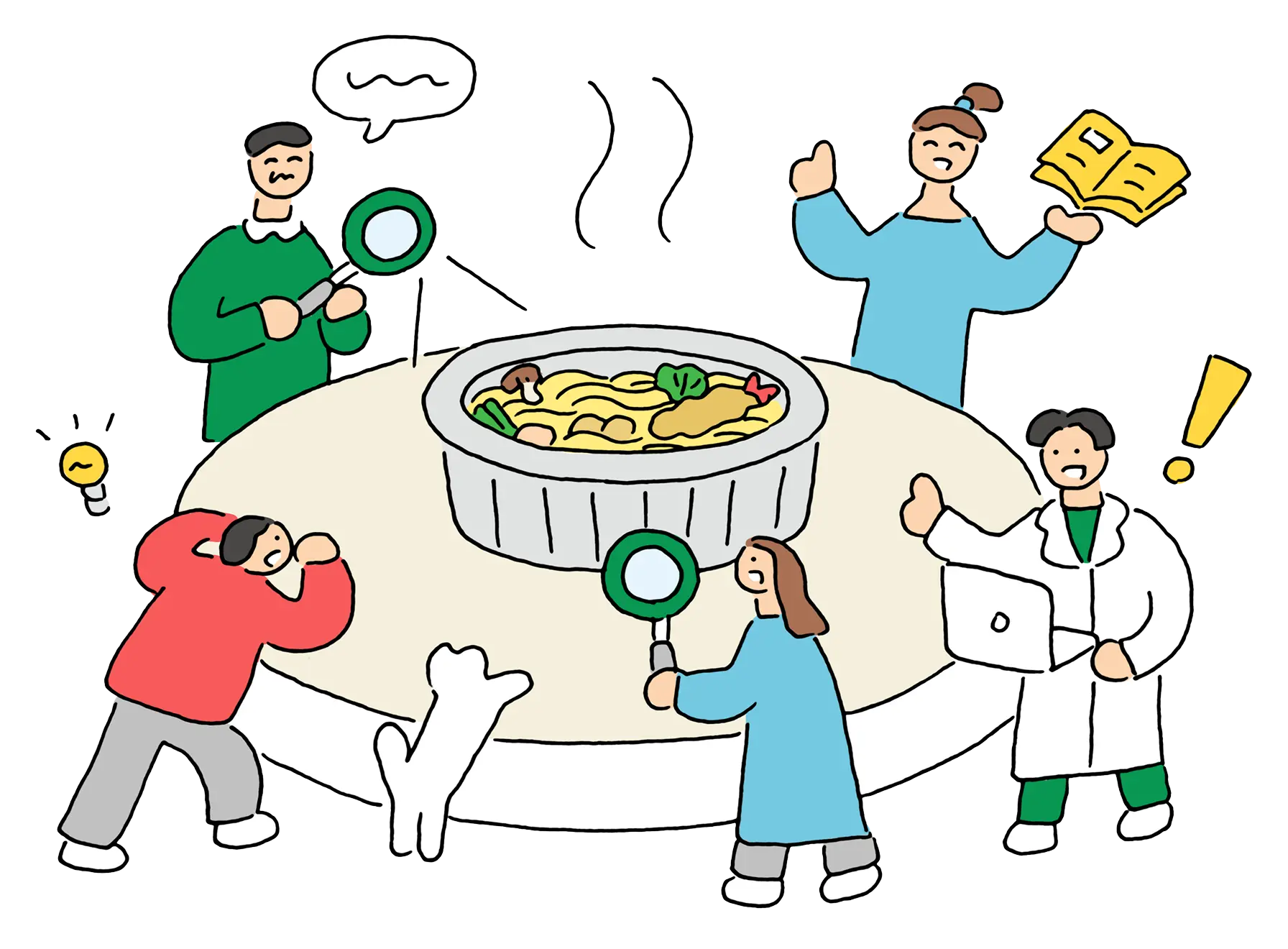
発見 15

商品開発部が目指すのは、パッケージの裏にある食品表示が、加工品ではなく「料理の延長」と感じられるよう、素材の名前が並ぶ誠実なものづくり。

キンレイ 商品開発部・角野
2018年3月入社、商品開発部所属。生まれも育ちもずっと大阪です。趣味は家庭菜園・旅行・ラジオでひたすら歩いて新しいお店を発掘するのも好きです。今のブームは発酵食品で、麹甘酒やみそ、ヨーグルトなどを自宅で作って楽しんでいます。特技は人の顔を覚えること、一度あった人は確実に覚えられます!
利益度外視のプロジェクトで見た、変わらない探究心
まず、角野さんのお仕事について教えていただけますか?
商品開発部でだしと具材の設計、そして商品の品質を保証する上で欠かせない食品表示(一括表示)の作成を担当しています。前職でも商品開発に携わっていましたが、キンレイに入社してすぐに感じたのは、会社の根本にある「おいしさ」への向き合い方の違いでした。
入社して間もなく、私はある特別なプロジェクトに参加することになりました。それが、社内の知見向上と理念の再確認のためだけに作られた『THE 鍋焼うどんプロジェクト』です。これは売り物ではありません。にもかかわらず、一年近くもの時間をかけ、日本中から最高の原料を探し出し、一切の妥協なく理想の味を追求する。利益に直結しない活動に、これほどの人と時間、そしてコストをかけるという事実に、まず大きな衝撃を受けました。
『THE 鍋焼うどん』は、冷凍食品というよりも、もはや料理でした。例えば、中に入っているえび天。私たちは開発室で一尾ずつ丁寧に背わたを抜いたえびの身に衣をつけて揚げるところから始めました。材料一つ一つにこだわり、素材に合った製法で仕込んだ鍋焼うどんはまさに専門店品質でした。
それから数年が経ち、今度は50周年記念キャンペーンの景品である『特製鍋焼うどん』の開発を担当することになりました。これはお客様にお届けする商品なので、工場のラインで生産することが前提です。そこには、『THE 鍋焼うどん』の時のような手作りとは違う、「工場生産ならではの制約」がいくつも存在します。先ほどのえび天で言えば、工場内で揚げ物をするのは安全面や工程管理の観点から非常に難しい。ですから、『特製鍋焼うどん』では、私たちがこだわり抜いて選んだプリフライ(揚げ済み)の天ぷらを採用しています。
もちろん、手揚げのおいしさには敵わない部分もあるかもしれません。しかし、その制約の中で、いかにして『THE 鍋焼うどん』で目指した本物の料理の味に近づけるか。それが私たちの挑戦でした。この二つの商品開発を通して感じたのは、変化ではなく、むしろ「変わらないな」ということです。たとえキャンペーンの景品であっても、おいしさのためなら一切妥協しない。この一貫した探究心こそが、キンレイらしさの根幹にあるのだと、私は確信しています。

答えはいつも「誰にとっておいしいか?」
開発者として特に大切にしていることは何ですか?
「おいしい」という感覚は人それぞれで、全国のお客様にお届けする以上、開発者自身の好みだけでは商品は作れない。これは、この仕事における永遠の課題かもしれません。
以前カレーうどんを試作した際、自分では「これだ!」と思う味に仕上げたつもりでメンバーに試食してもらったところ、「これは辛すぎるよ」と指摘されてハッとした経験があります。私自身、比較的辛いものが好きなので、無意識のうちに、自分好みに仕上げていたのかもしれません。自分の基準ではなく、食べていただくお客様の基準で味を設計しなくてはならないと、改めて痛感させられました。それ以来、試作でおいしいものができたと思っても、「これって本当にみんながおいしいと感じるだろうか?」「誰にとってのおいしさなんだろう?」と立ち止まって自分に問い直すことを心がけています。
独りよがりな設計に陥らないために、私たちは様々なアプローチを試みます。一つは、やはり多くの人の意見を聞くこと。そしてもう一つは、その料理の背景を徹底的に知ることです。
例えば、熊本ラーメンや尾道ラーメンといった地域性の強い商品を開発する際は、担当者が必ず現地に赴きます。ただ人気店の味を確かめるだけではありません。なぜ、そのラーメンがその土地で生まれ、人々に愛され続けているのか。その歴史や文化、風土といった背景まで深く掘り下げて調査します。その上で、「この味をキンレイの商品として表現するならば、どうあるべきか」という議論を重ねていくのです。
そうした試行錯誤の末に生まれた商品が、お客様の手に渡っていく。私たちの喜びは、その先にあります。社内には、お客様相談室に寄せられた声が共有される仕組みがあるのですが、その中には厳しいご意見も少なくありません。しかし、時折「以前販売していた『あんかけうどん』は、もう一度発売しないのですか?」「大好きだったので、また食べたいです」といったお便りが届くことがあるんです。終売となってしまった商品でも、わざわざ会社に連絡をくださるほど、その味を愛してくれた方がいる。その事実を知った時の喜びは、何物にも代えがたいですね。私たちの仕事は、ちゃんとお客様の食卓に届き、心に残っているんだと実感できる瞬間であり、開発者としての一番の励みになっています。
個人の技からチームの力へ、進化する開発の現場
おいしさへの姿勢は変わらない一方、変化していることはありますか?
キンレイのおいしさへの姿勢は変わりませんが、その実現方法は時代と共に進化しています。かつては、一人の開発者が一つの商品を突き詰めていくスタイルが主流でしたが、今は部署の垣根を越え、チームで課題解決に挑むことが増えてきました。
その象徴的な経験が、麺の入っていない新規惣菜メニューの開発です。これはお客様からのご要望で始まったプロジェクトでしたが、社内では前例がなく、特に工場での生産ラインにどう落とし込むかという点で、次から次へと課題が出てきました。自分一人では完全に行き詰まってしまった時、製造ラインのメンバーや他部署の専門家たちに助けを求めたんです。すると、それぞれの知見から解決の糸口が見え、少しずつ前に進むことができた。多くの人を巻き込むことで、不可能が可能になることを実感した、忘れられない経験です。完成後、知人から「お店で買って食べたよ、おいしかった」と連絡が来た時は、個人的にも本当に嬉しかったですね。
チームで開発するようになると、当然、意見がぶつかることもあります。面白いのは、開発の進め方にそれぞれの性格が出ることです。細かく重量を分けて緻密に何パターンも試作する人もいれば、まず両極端の味を作ってみて、そこからちょうど良いバランスを探っていく人もいます。試作品に対する味の解釈も様々です。
しかし、私たちの議論は、単なる好き嫌いの感情論にはなりません。先ほどお話ししたように、担当者はその商品の歴史的背景まで深く理解していますから、「こういう理由で、この味を目指している」というロジックがあります。意見が割れた時は、それぞれの考えを尊重しつつ、時には「言葉で議論するより、まず両方のパターンを作ってみよう」と、手を動かすことで答えを探しにいく。そんな文化が根付いていますね。
チームとしての知見を深めるための投資も惜しみません。定期的に著名な料理長をお招きし、大きな鉄鍋を使った本格的な調理講習会を開いています。本物のプロの鍋の振り方や火の入れ方を間近で学び、「おいしさのポイント」を体に叩き込む。こうした地道な探究の積み重ねが、チーム全体のレベルを引き上げているのだと思います。

私が守りたい、料理の延長線上にある味
最後に、角野さんご自身が守りたい「キンレイのおいしさ」とは何ですか?
会社の姿勢、チームの力、そして様々な探究。そのすべてを踏まえた上で、私が個人として守り続けたい「キンレイのおいしさとは何か?」それは、二つのことに集約されます。
一つは、最後の最後まで味を磨き続ける姿勢です。納期が迫っていても、「あと1ミリでもおいしくなる可能性があるなら」と、諦めずに試作を繰り返す。お客様には見えない部分かもしれませんが、その細部へのこだわりを失いたくない、という想いです。
そして、もう一つ。これが、私が最も大切にしている開発者としての哲学です。それは、商品の裏にある「一括表示」を見ただけで、「おいしそう」と感じていただけるものづくりをすること。
一括表示ラベルには、たくさんの原材料名が並んでいます。そこに、カタカナの聞き慣れない添加物の名前が延々と続くのではなく、皆様がご家庭のキッチンで目にするような、よく知っている「食材」の名前がきちんと並んでいること。それを見た時に、お客様はきっと「ああ、これは工場で作られた単なる加工品じゃなくて、ちゃんと人の手がかかった料理なんだな」と無意識のうちに感じていただけるはずです。どんなに技術が進歩しても、私たちの商品は、手間ひまをかけた料理の延長線上にある。その信念がお客様に伝わるような商品を、これからも一つひとつ、大切に届けていきたいと思っています。
関連記事

発見 16

おいしさを届ける、信頼と連携のバトン。
キンレイの製品を安定的に全国に届ける物流部。物を運ぶだけではない、多岐にわたる調整と予測、そして現場との連携。

発見 17
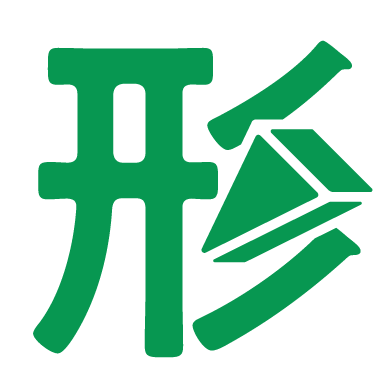
品質と生産効率のバランサー。
わずか数グラムの差が、おいしさを変えてしまう。品質と効率のはざまで、お客様の信頼に応え続ける生産部の挑戦。

発見 18

矛盾する原価管理とおいしさの追究。
商品の品質と価格のバランスに独自の視点を持つ経営企画。矛盾する中でもおいしさを守る上で大切にしていること。