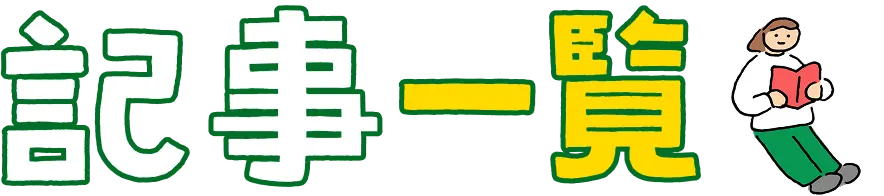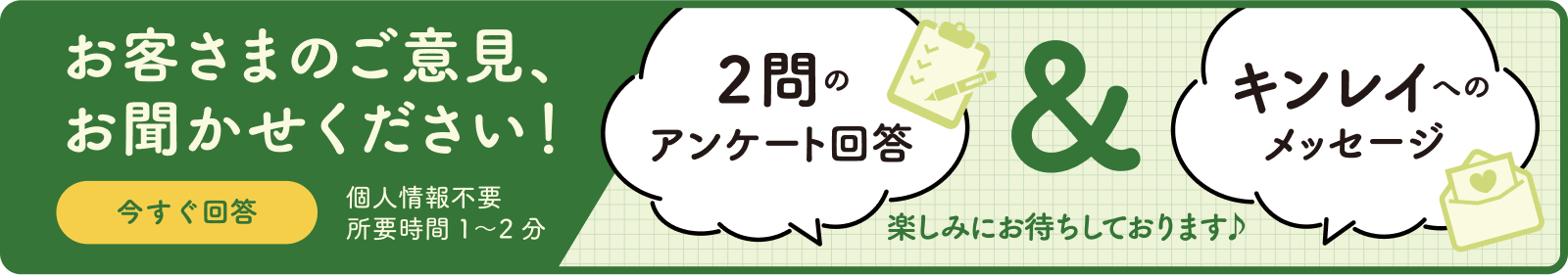おいしさを届ける、
信頼と連携のバトン。
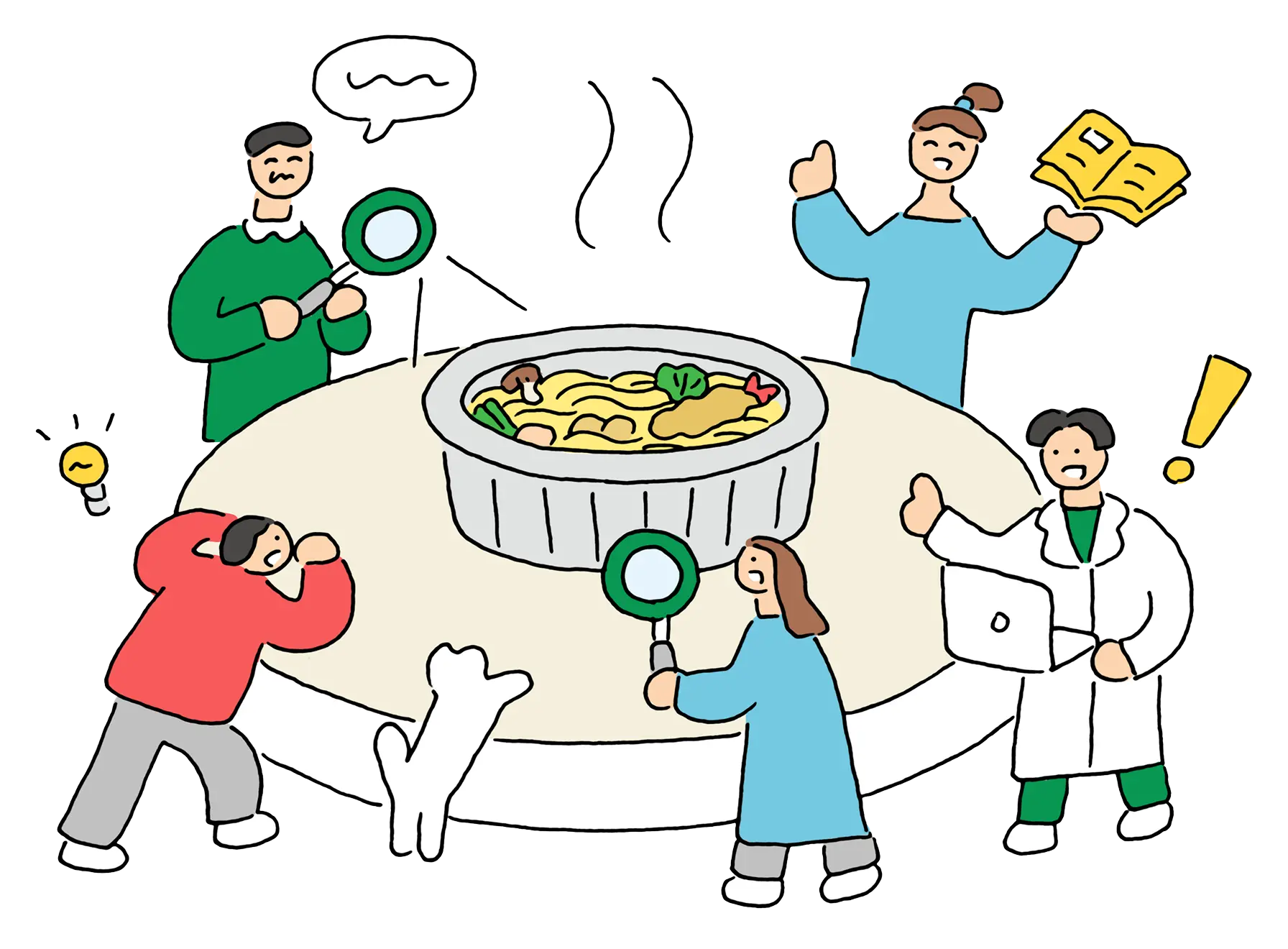
発見 16

キンレイの製品を安定的に全国に届ける物流部。物を運ぶだけではない、多岐にわたる調整と予測、そして現場との連携。

キンレイ 物流部・古井
前職でも物流業務に携わっていたこともあり、入社当初から物流部門(当時は「需給管理課」という部署名でした。)に所属。以後物流業務・生産計画業務に長年従事しています。
二郎系ラーメン巡り(直系20店舗訪問済)とサウナ巡り(700店舗訪問済)とマラソン(目指せサブ4)が趣味。ランニングでサウナに向かい、その後二郎を食べます。一番良かったルートは錦糸町ニューウイングまでランニングからの亀戸二郎。二郎には生卵必須派。
食卓へ届ける当たり前を、支える
物流部の役割について教えてください。また、その中で古井さんが担っていることはどのようなことですか?
物流部の仕事は一言でいえば「物を運ぶ」ことですが、それはただの輸送ではなく、お客様のもとへ当たり前に商品を届けるということなんです。工場でつくった商品を一度倉庫に入れて、そこから問屋さんに届ける。全国の倉庫にバランスよく在庫を配置して、品切れにならないようにするのが私たちの役割です。
それに加えて、生産スケジュールの立案も物流部が担っています。営業からの情報をもとに、月単位・週単位の計画を立てるだけでなく、1〜2年先を見越した中長期のスケジュールも組みます。工場や販売、材料部門と密に連携しながら、どの商品をいつどこでつくればいいのかを逆算して計画していく。この調整が、キンレイのおいしさを安定してお届けするための基盤になっています。
長年の信頼が紡ぐ、確かなお届け
全国の倉庫との関係づくりも物流部の大切な仕事の一つだと思いますが、特に意識していることはありますか?
キンレイの商品を預けている全国の寄託倉庫さんとは、月に1回は販売動向や物流動向について情報交換を行っています。人と人とのやり取りを大切にするのが、キンレイの物流部らしさだと思っています。
特に、創業当時からお付き合いのある倉庫さんとは長い歴史があります。信頼関係がしっかりあるからこそ、大切な商品を安心して預けることができるし、臨機応変な対応もしていただける。人の力が支えてくれている現場です。
進化し続ける物流
2024年問題など、物流業界を取り巻く環境が大きく変わってきています。その中で、どのような取り組みをされているのでしょうか?
確かに、商品の配送や、材料の調達も以前よりずっとシビアになってきました。たとえば、原材料の仕入れでは、これまで1ヶ月先を見ていればよかったところが、今では2ヶ月、3ヶ月先の判断が必要になっています。配送も、昔は翌日届いていた荷物が、今は翌々日になったりと、物流のスピード感も変わってきました。
そうした中で、私たちは取引先様にご協力いただき、発注データを従来より1日早く寄託倉庫様にお伝えする形にし、寄託倉庫様の配送効率・作業効率の改善に貢献していきます。また、積み込みや荷降ろしの時間も、時間予約制にすることで、ドライバーさんが倉庫や工場で長時間待たされないよう改善しています。これらの取り組みを通じて、持続可能な物流を目指しています。

部門間の連携が織りなす、おいしさのバトン
おいしさを届ける上で、物流としてこだわっていることは何ですか?
例えば営業は「欠品しないようにたくさん作ってほしい」、購買は「原材料を安定して仕入れるために、早めに計画を決めてほしい」、工場は「効率よく生産したい」と、それぞれの立場での要望があります。その中で、すべての部門にとっての「一番の落としどころ」を見つけて計画に落とし込んでいくのが、難しくもあり、腕の見せ所でもあります。
特に最近は、原材料の調達が難しくなったり、配送のルールが変わってリードタイムが長くなったりと、外部環境の変化が激しいんです。以前なら1ヶ月前に決めればよかったことが、今は3ヶ月先まで見通して判断しなくてはならない。予測の精度を上げるために、僕らが一番大切にしているのは、関係部署との密なコミュニケーション。数字だけでは見えない現場の状況を直接ヒアリングすることで、計画の精度を上げています。
「おいしい」を運ぶやりがい
最後に、古井さんにとっての仕事のやりがいを教えてください。
前職ではセメントなど、最終的に誰の役に立っているのかが見えにくいものを扱っていました。でも今は、自分が計画を立てて運んでいる商品が、スーパーに並んで、誰かの食卓でおいしく食べられている。その顔が見える感じが、すごくやりがいにつながっています。
お昼にキンレイの商品を食べて、「ああ、これは自分が運んでいるものなんだな」と感じられる。当たり前のようですごく嬉しい瞬間です。僕たちの仕事は、なかなか表舞台に出ることはありません。でも、お客様がいつでもおいしい商品を手に取れる「当たり前」を支えている。その自負が、日々の仕事の原動力ですね。
関連記事

発見 15

問い続けるのは、誰にとってのおいしさか?
商品開発部が目指すのは、パッケージの裏にある食品表示が、加工品ではなく「料理の延長」と感じられるよう、素材の名前が並ぶ誠実なものづくり。

発見 17
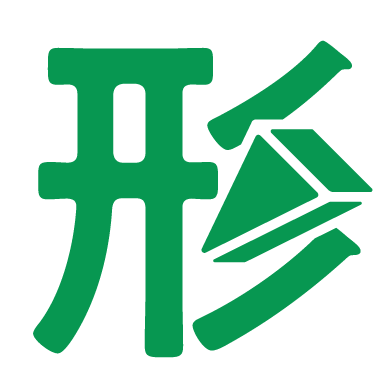
品質と生産効率のバランサー。
わずか数グラムの差が、おいしさを変えてしまう。品質と効率のはざまで、お客様の信頼に応え続ける生産部の挑戦。

発見 18

矛盾する原価管理とおいしさの追究。
商品の品質と価格のバランスに独自の視点を持つ経営企画。矛盾する中でもおいしさを守る上で大切にしていること。