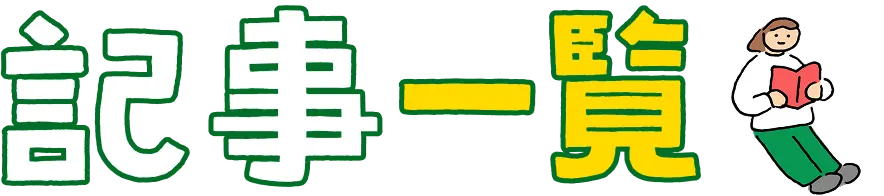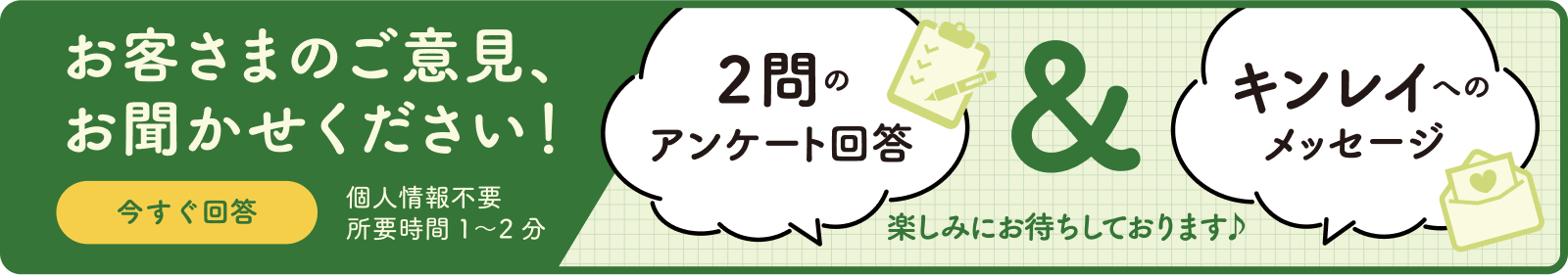変わらない風景をつくる、
一杯の鍋焼うどん。
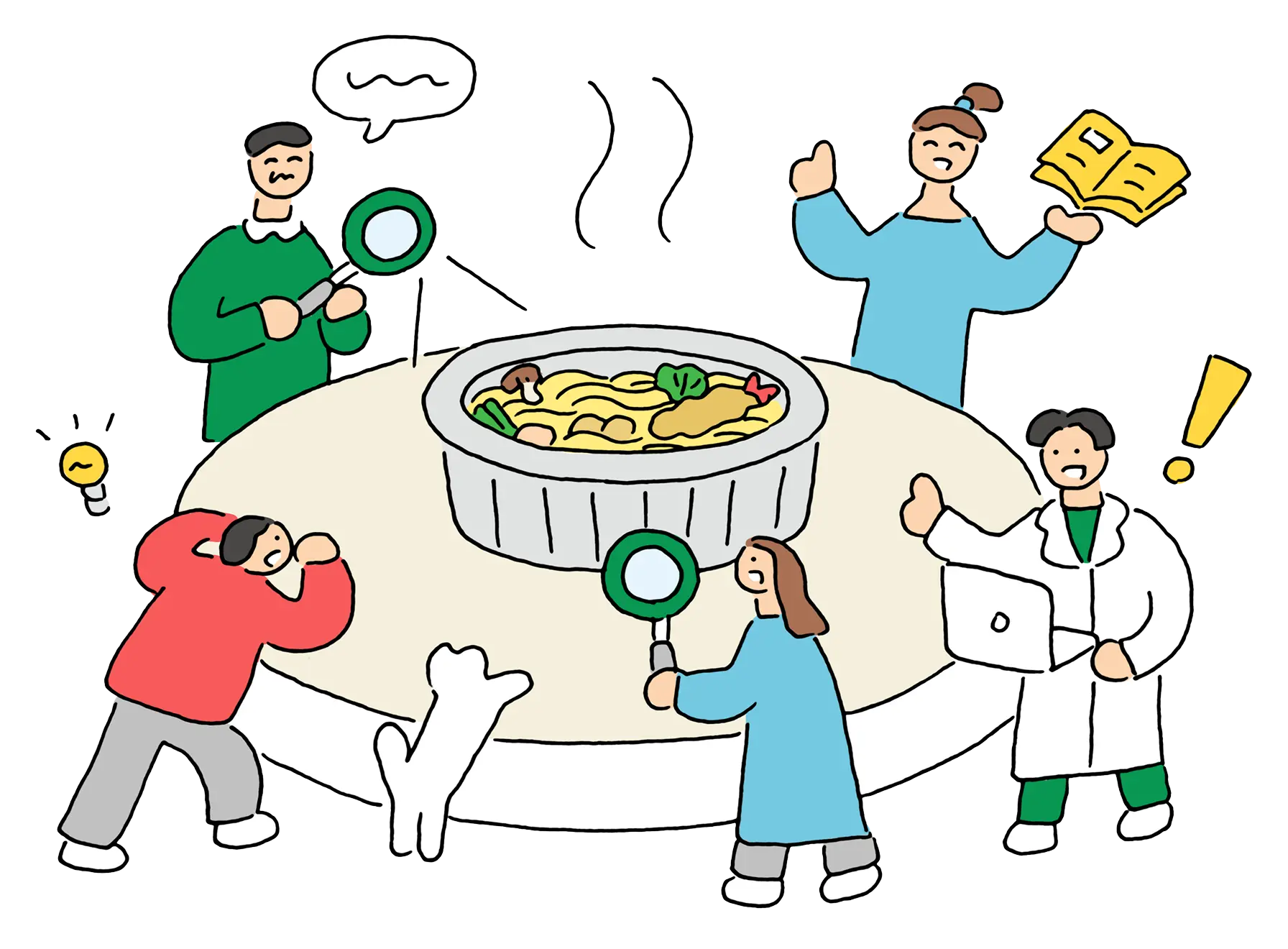
発見 13

冷凍食品にそこまでやる?キンレイの常識は、業界の非常識。でも、妥協しないからこそのおいしさがあると私たちは知っています。冷凍の鍋焼うどんをめぐる、熱い物語です。
お客様の思い出とともに50年。キンレイ魂の出発点がこれでした
“子供の頃、風邪を引くと母が鍋焼うどんを食べさせてくれました。これ食べたら治るよと言われ、ふぅふぅしながら熱々を食べると不思議と元気になっていました。私にとって鍋焼うどんは、おいしい魔法の食べ物です。”
これは、お客様から届いた鍋焼うどんへのファンレターです。1975年に発売されたアルミ容器入りの「鍋焼うどん」。子どもの頃に食べた方には、同様の記憶を持つ方は多いはず。「テスト中の夜食にお母さんが作ってくれた」「日曜日にお父さんと2つ並べて煮込んだ」「食欲がないときも、おばあちゃんが作る鍋焼うどんはおいしかった」──各家庭で煮込んで完成させるからこそのおいしさと思い出が、湯気の向こうに見えてきます。
最近は「キンレイといえばラーメン」とイメージする方も増えてきました。新たな道を切り開けたことに喜びを感じると同時に、「アルミ鍋に入ったあの鍋焼うどん」を世に送り出し、50年以上もの長きにわたって愛されているという事実は、やはり「なべやき屋」としての誇り。事実、ラーメン人気が高まる中でも、キンレイ商品で一番売れているのは「鍋焼うどん」です。
キンレイってどんな会社?と問われれば、「とにかくおいしいものを作る」という一点を見据えて、泥くさい努力を重ねているものづくりの会社と言えます。「おいしさ」という、至極個人的に思える感覚を多角的かつ科学的に分析し、方向性と目的を明確にしながら実践し、納得できる「おいしい」に到達するまで何度でも改良する。それがキンレイのDNA。
その出発点となったのが、鍋焼うどんでした。業界の常識を知る人からは「なんでそんなにこだわるの?」「そこまでやって大丈夫?」と半ば呆れられるほどの想いとこだわりが詰まった結晶なのです。
最高においしかった初代の味。目指すのは常に「その先のおいしさ」
初代「鍋焼うどん」を知る人は「とにかくおいしかった」と口を揃えます。あれから50年を経た今、私たちが取り組んでいるのは「初代の再現」ではありません。あのおいしさをつくり出せた心意気を胸に深く刻み込みながら、「お店の作り立ての料理以上においしい」と喜んでいただけることを目標に、常に「現時点でのベスト」を狙っています。
そんな日々の中に、「もう、このへんでいいか」という妥協はありません。専門店の厨房のように手間のかかる工程を当たり前のように選び取っています。
まず、味の決め手となるだし 。目指しているのは、食材が持つピュアな旨みや甘みを丁寧に引き出した、底力がある中にもクリアで上品な味わいです。小麦から出る風味や具材の旨みも考慮して、煮込んだとき最高の状態にすることが使命なので、何かひとつを突出させるのではなく、それぞれを活かしながら黄金比を探していきます。

たとえば節類は、加工済みの削り節を使うという常識を打ち破り、自社工場内で削ります。豊かな風味が際立つメリットはもちろん大きいのですが、酸化による雑味をできる限り抑えたい、という意図もあります。節類は削ってしばらく経つと独特の酸味や生臭みが出るため、使う直前に削ることでそれを防ぐのです。
昆布の調理法もかなり独特です。工場の鍋は人がすっぽりと入る以上の大きさ。この大鍋で炊き出した後に昆布を1つずつ取り出すのは至難の業なので、当初は束ねた状態で煮ていました。しかし現在は、巨大なひっかき棒のような道具を自作し、一枚一枚をお湯の中で泳がせるようにしています。昆布の深い旨みを十分に引き出すには、このやり方しかないとわかったからです。

こうした常識破りのひと手間を挙げていけばキリがありません。でもそのすべてが、キンレイにとっては目指すおいしさに到達するための必然なのです。
冷凍食品というと「工場で大量生産」のイメージが強いかもしれませんが、キンレイの場合は「厨房での調理」という印象。非効率的な工程をあえて選び取るストイックな姿勢の背景には、「お店のおいしさを冷凍麺で目指したい」という想いがあります。何ひとつ妥協することなく、「もっともっとおいしくするには?」と常に進化する気持ちが日々の現場を支えているのです。
だし・麺・具材のすべてにこだわって、一杯のうどんが完成
こうして生み出される鍋焼うどんのだしは、大阪を発祥とするキンレイらしく、関西風のまろやかな香りと旨みが特徴です。より良い素材・製法を追求して改良していく中でも、「節・昆布・椎茸」というベースの方向性は不変。淡口醤油が主体となる味付けを邪魔しないよう、だしとしての個性を主張しすぎることなく、料理として全体がおいしくなるように。そんな想いで仕上げています。
そして、鍋焼うどんの主役はなんといっても麺です。いくらだしが良くても、麺自体が「本当においしい」状態になかったら、冷凍食品としての価値はありません。
冷凍してから煮込んでも、小麦の香りとほどよい食感を損なわないこと。そのために良質な国産小麦を厳選し、最良の配合で製麺するのはもちろんのこと、具・麺・だしの三層を解凍順に重ねる「三層構造」によって、温めた際ベストな状態に仕上がる設計も生み出しました。

もうひとつの要は、具材です。麺もだしもおいしい。でも、「そこに載っている具が何より楽しみ!」という方も多いはず。その期待を裏切らないよう、見た目や彩りだけでなく、煮込まれた際にそれぞれの味がだしにどう作用するかまで計算しています。こだわりのタレで下味を付けたやわらかい鶏肉、とれたての旨みをそのまま味わえる海老、干し椎茸をふっくら戻した戻し汁で含め煮する椎茸など、「選りすぐりの素材+妥協知らずの調理+キンレイならではの冷凍技術」をフル活用した、自慢のラインナップです。
鍋焼うどんは、煮込んでこそ完成する料理です。家庭でグツグツ火にかける時間とともに、だし・麺・具材すべての味わいが重なって一体化していく。だしにも麺にも具材にも、何ひとつ手を抜かない開発の現場で常に意識しているのは、「最後にみなさんの食卓で召し上がっていただくときの完成形」なのです。
誰かの温かい食卓に寄り添える「鍋焼うどん」をこれからも
キンレイでは2014年から、「理想の鍋焼うどん」を追究する研究会を社内で続けています。価格や調理法などの制約をいったんすべてなくし、「本当のおいしさって何だろう?」という理想を探るのです。新商品を開発するために、というよりも、鍋焼うどんという料理一品の完成度を今以上に高めていき、結果として、お客様にもっともっと喜んでいただくことが目的です。
たとえば椎茸ひとつを取っても、どの産地がいいのか、どんな厚みに切ればおいしいのか。すべてを見直し、素材をひとつずつ調べ上げて、最適な組み合わせ・成長のポテンシャルを見極めていきます。
その過程で、「ただただ贅沢な食材を組み合わせれば完成する、という単純なものではない」「だし、麺、具材。それぞれが絶妙なバランスで調和して初めて、心に残る一杯になる」ということを、深く学び直す機会にもなりました。
こうした研究活動を通じて、これからの技術を伸ばす足場を固めながら、「料理を科学する」という開発姿勢も、より強固に育んでいます。おいしさのポイントを突きつめること、それをロジカルに分析して可視化すること。その両輪で進み続ける姿勢こそが、手作りのおいしさをより多くの人に届ける結果につながる、と信じています。
鍋焼うどんには、記憶を呼び起こす力があります。グツグツと煮える音、立ちのぼるだしの香り、湯気の向こうに見える具材の彩り。そして、作ってくれる誰かの笑顔。熱々のところをふぅふぅ冷ましながら食べていると、「あのときの風景」がよみがえってくるような、あるいは、体の奥から元気が出てくるような、そんな料理だと思っています。
何でもない一日にも、体調を崩した日にも、寒い冬の夜にも。何気ないけれど温かい食卓に、キンレイの鍋焼うどんがお供できたら。そして、食べた人を「おいしい笑顔」にできたら──。
50年間ずっと、私たちはその思いを持ち続けていました。これからも、変わらない食卓の風景と温かい記憶を届けたくて、キンレイは変わり続けます。