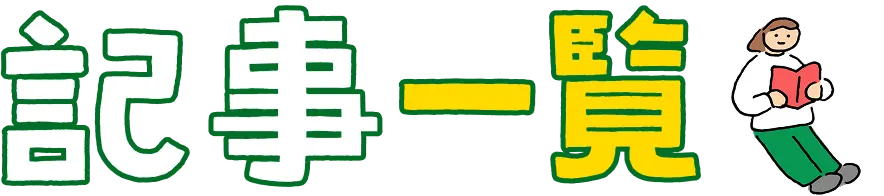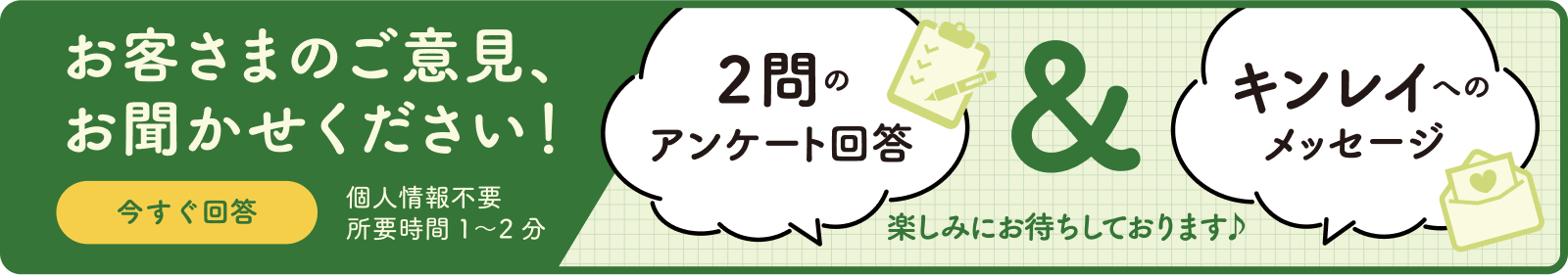鍋島焼に学ぶおいしさ
土地の営みが育む、ものづくり
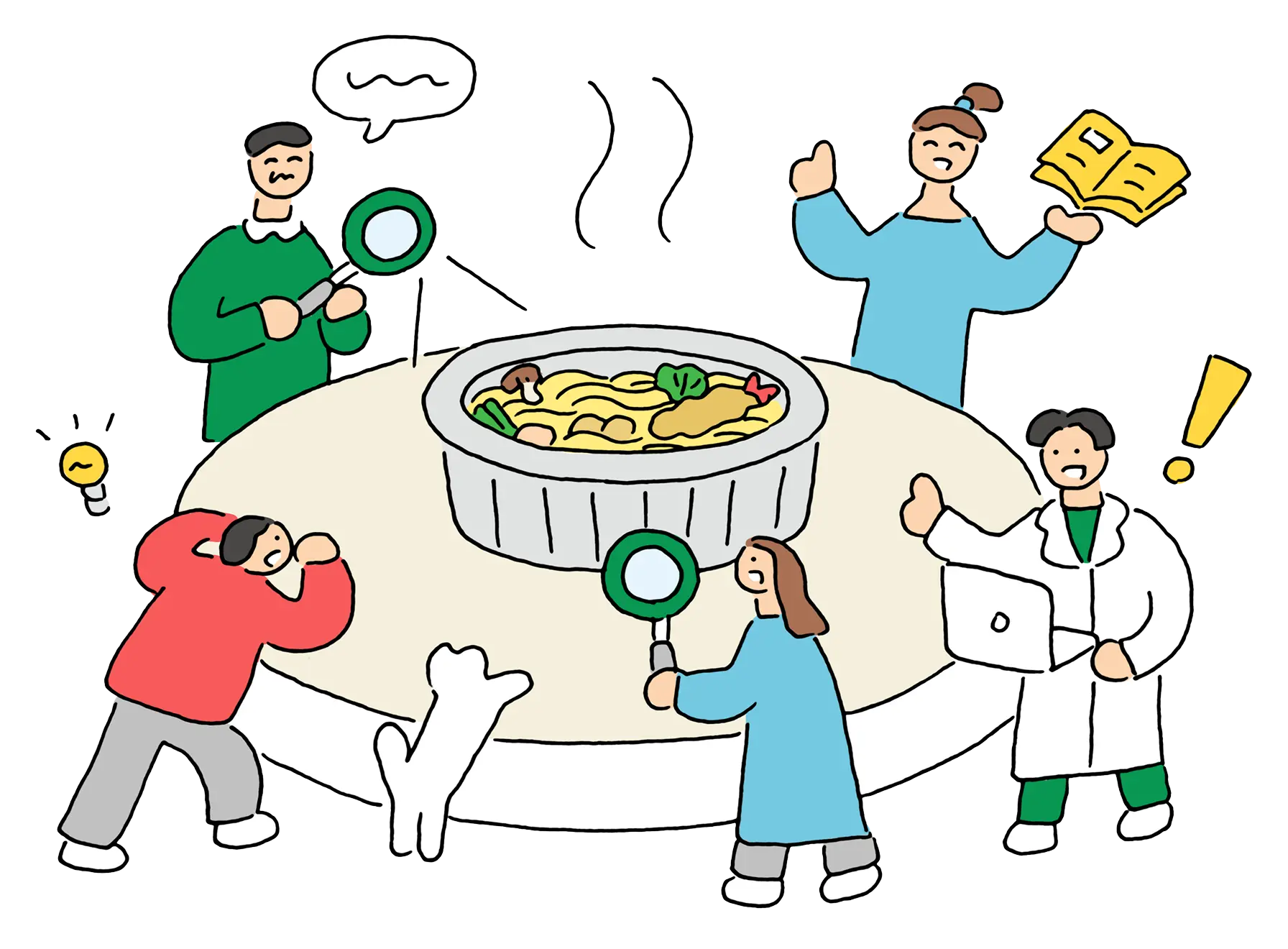
発見 23

「手仕事だから価値がある」は本当か?冷凍食品のキンレイが、伊万里の窯元で見つけたおいしさの先の答え。ものづくりの本質とは。

鍋島虎仙窯三代目・川副 隆彦
株式会社鍋島藩窯百撰 代表取締役。有限会社杏土窯 代表取締役。伝統工芸士・一級技能士の資格を取得し350年以上の歴史を持つ鍋島焼の産地・大川内山で、伝統と現代デザインを融合させたものづくりに取り組む。
2025年、鍋島焼開窯350周年事業実行委員長として産地の未来を担う活動を展開。文化と経済の両立を掲げ、地域資源を活かした新たな価値創出を目指している。

キンレイ営業本部(企画部マネージャー)・大倉
育ちは京都、社会に出てからは東京・奈良などで暮らす。旅先で器やアンティークを物色するのが趣味。キンレイでは、商品の企画・デザインやブランドのコミュニケーション設計などを担当しています。
キンレイ50周年を記念し、特別なキャンペーン賞品をご用意しました。佐賀・鍋島焼の窯元「鍋島虎仙窯(なべしまこせんがま)」が手がける、美しいオリジナルカラーの丼です。鍋島焼とは、江戸時代に将軍家へ献上された特別な焼き物。中でも虎仙窯の青磁は、この土地でしか採れない天然の原石から釉薬を手づくりする、大変希少なものです。しかし、あまりの量産の難しさから、これまでその器が食卓に並ぶことはほとんどありませんでした。虎仙窯は「この美しさを、特別な日だけでなく日常でこそ味わってほしい」という想いで、長年かけて量産できる技術を確立しました。
ものづくりへの姿勢がつないだ縁
今回の取り組みは、キンレイ50周年キャンペーンの賞品製作を虎仙窯にお願いしたことから始まりました。川副さんは、私たちのものづくりに対する姿勢に共感してくださったといいます。
「キンレイさんからお話を聞いた時、モノの良し悪しや値段の話以上に、みなさんの思想的な部分、ものづくりへの取り組みや姿勢に強く共感したんです。それが一番大きかったですね」
虎仙窯では、条件だけで仕事を選ぶことはありません。互いの哲学を理解し、尊重し合える関係を大切にしています。
「僕らの取り組みや姿勢に共感してくださる方々と、仕事をしたい。そうずっと思ってきました。キンレイさんは、食というジャンルは違えど、本質を追究し、文化を未来へ繋ごうとしている。その姿勢に、嬉しくなりました」
「思想への共感」それが、今回の特別な丼が生まれるきっかけでした。では、虎仙窯が大切にしている思想とは、どのようなものなのでしょうか。その原点は、ある違和感だったと川副さんは語ります。

「美しさとは何か」という問い
「『三百年の歴史』『職人の手仕事』。かつては、私たちもそうした言葉をよく使っていました。でも、どこかでその言葉の軽さに違和感があったんです」
川副さんが家業を継いだ頃、良いものを作っていれば売れるという時代は終わりつつありました。経営の危機に直面し、「自分たちは何のためにこの仕事をしているのだろう?」と自問する日々。その中でたどり着いたのが、「鍋島焼文化の確立」というビジョンでした。それは、伝統的な器の形や技法を守るだけでなく、もっと本質的な「美しさとは何か」を問い続けることでした。
「『手仕事だからすごい』『歴史があるから価値がある』と、思考停止で語るだけでは人の心には響かない。歴史があることが、今の暮らしにとって本当に価値があるのか。そこを突き詰めて考え、自分たちの言葉で語れなければ、未来はないと感じました」
この真摯な問いから、虎仙窯の哲学は深まっていきます。器そのものだけでなく、それを生み出す背景にこそ、美しさの本質があるのではないかと。


「営み」という考え方
「私たちは、ものづくりが一番上にあるとは考えていません。あらゆるものの根底にあるのは、この土地で暮らす人々の『営み』です」
この言葉に、虎仙窯の哲学が表れています。かつてものづくりは、暮らしを豊かにするための「手段」でした。しかし、いつしかものづくりそのものが「目的」となり、作り手の暮らしや産地の環境を疲弊させてしまうことがある。それでは本末転倒ではないか、と川副さんは指摘します。
「右肩上がりの経済成長だけが、僕らの理想ではありません。文化的成長と経済的成長を「51:49」くらいのバランスで、少しずつでも前に進めていく。地域の草刈りのような地道な活動も含めて、この産地ならではの豊かさを、自分たちで作り上げていきたいんです」
さらに、虎仙窯では「暮らし」という言葉を、より広い意味を持つ「営み」という言葉で捉えることを意識しています。
「『暮らし』と言うと、その土地の住人だけに限定されがちです。でも私たちの文化は、住人だけでなく、関わってくれるデザイナーやカメラマン、地域の専門家など、多くの人々との関係性の中で成り立っています。その活動全体を、私たちは『営み』と呼びたい。この『営み』自体を豊かにしていくことが、本当に良い器を生み、文化を未来へ繋ぐ道だと信じています」

もがき苦しむ道を選ぶ。350周年の節目に懸ける想い
文化を守るという壮大なビジョンの裏側で、川副さんは今、産地が抱える根深い問題に真正面から向き合っています。
「実はこの地域には、長年の根深い問題があります。鍋島焼は『献上品』としての文化を持つ一方で、同じ伊万里市で作られているため、広く知られている『伊万里焼』という名前で売られることも多い。行政も観光PRでは伊万里焼を打ち出したい。文化的には全く違うものが、経済的な理由で混同され、ブランディングが非常に曖昧になってしまっているんです」
次の世代に問題を先送りにはできない。その強い想いから、鍋島焼組合では鍋島焼350周年の節目に、「鍋島焼」としてのブランドを整理・統一していくことを宣言。産地内での課題もありながら、未来のために議論を重ねる日々だと言います。それは、決して平坦な道のりではありません。
「1000年続いた祭りが、担い手不足から『美しく散る』という選択をした例もあります。それも一つの判断だと思います。でも僕らは、もがき苦しみながらでも、やり続けることを選びました。そのプロセスにこそ、ものづくりに携わる人間の美学があるんじゃないかと。悩み、行動し、言葉にし続ける。その積み重ねが、僕らのビジョンの厚みになっていくと信じています」
ものづくりへの真摯な姿勢、そして文化を未来へ繋ぐという覚悟。その熱を帯びた想いに、私たちキンレイも強く心を動かされました。
「今回、キンレイさんとご一緒させていただくことになったのも、僕らのものだけでなく、その背景にある思想や取り組みに共感していただいたことが大きかった。食という、生活の中心にあるものを通して、鍋島焼という文化に触れてもらうきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません」

美しさとおいしさが重なる場所
虎仙窯の「営み」という考え方に、私たちは深く共感しました。キンレイが50年間追い求めてきた「おいしさ」もまた、この「営み」の中にこそ存在するのではないか、と。
一杯のうどん。それは、素材だけでできているわけではありません。生産者の営み、開発者の営み、工場の従業員の営み、そして食卓を囲む家族の営み。そのすべてが繋がり、キンレイの「おいしさ」は生まれています。
虎仙窯が「美しさとは何か」と問い続けるように、キンレイは「おいしさとは何か」と問い続ける。どちらも、スペックや成分表では表現できない、人の心を満たす価値を追究する旅です。ものの背景にある物語や体験にこそ価値があるという共通認識が、私たちと虎仙窯をつないでくれました。

関連情報

50周年大感謝祭プレゼントキャンペーン
-
キンレイ50周年を記念して、虎仙窯さんにキャンペーンの賞品として特別な器をつくっていただきました。美しいキンレイオリジナルカラーの丼です。この記事で語られた、ものづくりへの想いが詰まったこの丼は、いつもの食卓を少し豊かにしてくれるはずです。普段はこうした取り組みをほとんどされていない虎仙窯さんが、一つひとつ丁寧に仕上げてくださった、この機会だけの特別な器。50年の感謝を込めてお贈りします。ぜひキャンペーンにご応募ください。お待ちしております。

鍋島虎仙窯
-
江戸時代に将軍家へ献上されていた鍋島焼。その技術と文化を継承し現代の暮らしに合ううつわを作りながら、百年後の未来に向けて鍋島焼文化を確立するための活動に取り組んでいる。
関連記事

発見 14

50年の集大成と未来への挑戦黄金だしの特製鍋焼うどん
50周年を迎えたキンレイが「今のベスト」として贈る特製鍋焼うどん。ものづくりの魂を余すところなく詰め込んだその一杯は、食べる人の五感を包み込む。集大成であり、未来への挑戦でもありました。

発見 22

はじまりは恩送り四海樓ちゃんぽんの126年
ちゃんぽんは単なる料理ではなく、理念を具現化したもの。そう語るのは発祥店「四海樓」の陳優継さん。126年の歴史と込められた想いを伺いながら、キンレイのロングセラー開発秘話に迫ります。

発見 01

50年の感謝と次の一杯へ
変わらぬ想い、おいしさで世界とつながる未来へ──。50周年を迎えたキンレイ代表の白潟より、感謝と新たな決意を込めたメッセージをお届けします。