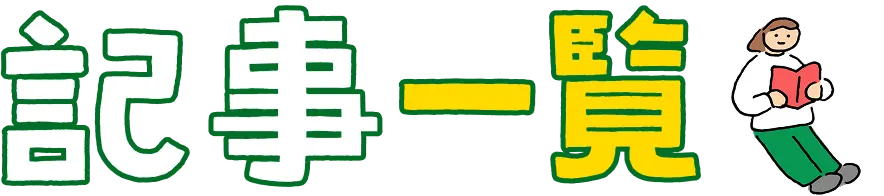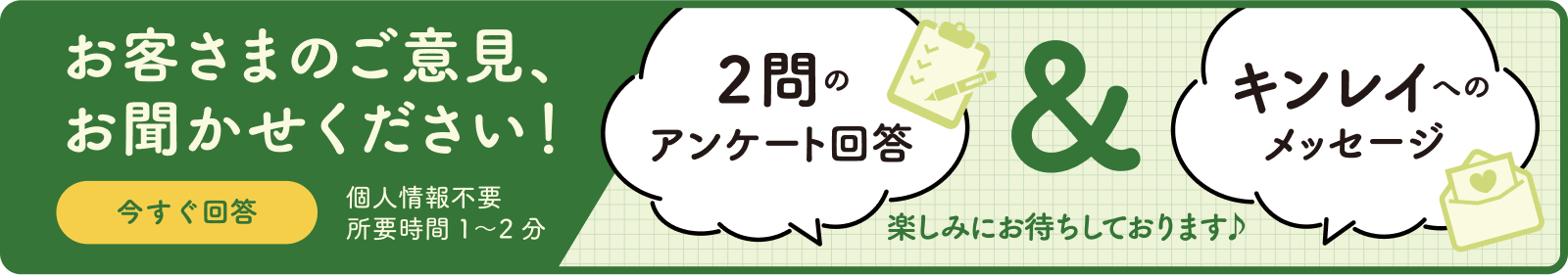組合員の声を大切にする、
コープ商品とのものづくり。
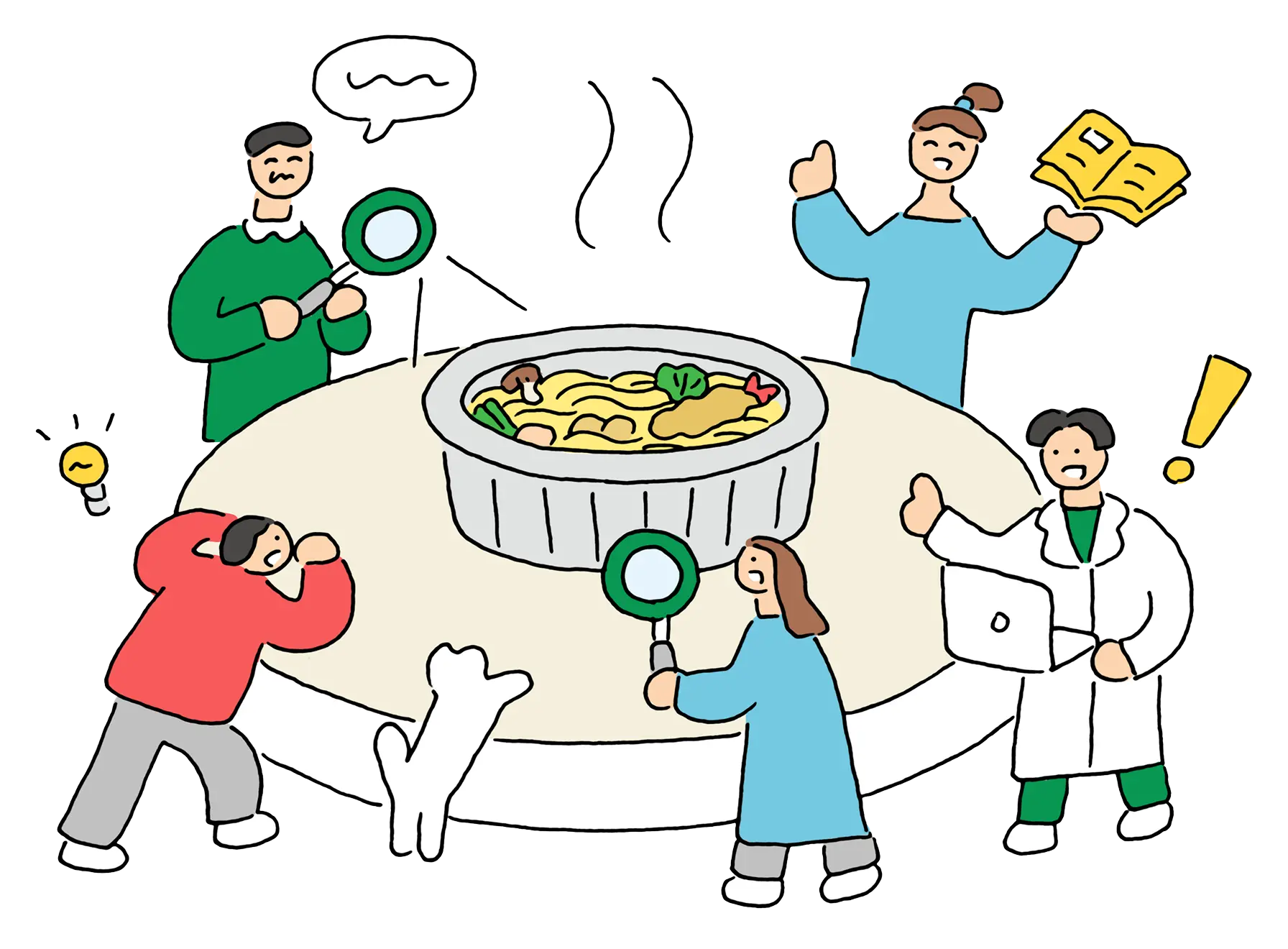
発見 21

生協とキンレイは長年「組合員のみなさまが求めるおいしさ」をともに追究してきました。今や冷凍麺カテゴリーの売上No.1を誇る長崎風ちゃんぽんを中心に、担当者2人が本音で語ります。

日本生活協同組合連合会 第一商品本部・ 藤田さん
2020年1月から第一商品本部に配属。2021年度・2022年度に冷凍麺を担当し、新商品の開発や大型商品「CO・OP長崎風ちゃんぽん」のリニューアルなどに携わる。一日3麺もいとわない生まれついての麺好きで、担当を外れた今でもキンレイの新商品は欠かさずチェックしている。

キンレイ営業部・澤田
1978年、鍋焼うどんと共に生まれた46歳。キンレイには2009年に入社。前職も食品メーカーで、その経験を活かして量販営業の新規開拓に従事。2013年、マネジャーとなり東京へ。2015年に初めて生協さん担当となり、コープ商品の開発等に携わる。2019年からは営業部長として、日々キンレイのものづくりのすばらしさを提案しています。
コープ愛 × キンレイ愛。妥協しない両者が目指すもの
藤田さん(以下敬称略)
実は、冷凍麺を担当する前から、根っからのキンレイファンなんです。とくに、母方の実家が西日本にあることもあって、鍋焼うどんは慣れ親しんだ味で大好きです。初めて大阪工場に伺ったとき、鍋焼うどんの工程を確認する必要はなかったのにわざわざ寄り道させていただいて、昆布だしを取るための巨大な釜を見せてもらいました。丁寧に作業される姿を見て「本当にここまでやるんだ!」と感動しました。
澤田
いきなりありがとうございます(笑)。藤田さんが担当になられたのは2021年。私は当時、営業担当者の上司という立場でしたが、多くの突破口を作っていただいたと思っています。我々の言っているポイントを理解しながら、ご自身の軸も決してぶれず、一緒に進んでくださったのが心強かったです。
弊社の当時の担当者もかなり頑張っていて、細かいところまでぶつかり合いながら…でしたね。
藤田
一歩も譲らずでしたね、お互いに(笑)。
澤田
互いの信念の元に主張し合って、削ぎ落としながらいいものを作っていく、これができるのは理想的だと私は思ってるんです。でないと、いいものなんてできないですから。
そもそも生協という組織は、組合員になってくらしを応援するという社会貢献の意味も含めた共同体なので、そこに対する想い、いわば「コープ愛」がある方たちばかり。藤田さんのような働く側の人もそうだし、組合員さんにもコープ愛があります。そして弊社にも「キンレイ愛」が社員にもお客様にもあると思っています。だからこそ、よりおいしくしたい、そのための手間は惜しまない、というところに共通項があるのかなと。たとえば、商品の見せ方ひとつにしても、藤田さんのこだわりはすごかったですよね。
藤田
商品写真には相当こだわりました。パッケージ写真って宅配用の誌面ではかなり小さくしか載りません。そのほかに調理のイメージ写真も掲載しますが、そこでおいしさが伝わらないと買っていただけない。「こんなにこだわって、こんなにおいしいものができたのに」という想いがあるので、それが伝わらないなんてもったいなくて。
澤田
しかもその写真で、ちゃんと売上が変わるんです。そういう細部にこだわる人はほとんどいらっしゃらないので、印象的でした。

組合員の声を大切にする姿勢がなければ、今のちゃんぽんはなかった。
澤田
コープ商品は、とにかく組合員のみなさまの声、通称「組声(くみこえ)」を大切にされます。私はその姿勢に共感しますし、それらの膨大なご意見を我々にも開示した上で「だから、ここをもっと良くしたい」と相談いただけることがとてもありがたいと思っています。
「CO・OP長崎風ちゃんぽん」のリニューアルにも「組声」が活かされていますよね。
藤田
はい。組合員のみなさまからのご意見、本当にたくさん寄せていただきます。普通はお申し出的な内容のほうが声を上げる動機になるものですが、生協の場合は「あれがおいしかったよ」「こんな使い方をしてみたらすごく良かったから他の人にも伝えて」など、いい声が集まるのが特長です。ちゃんぽんにまつわる大好きなエピソードがありまして。その方はお母様が九州の方で、「お母さんが作るちゃんぽんが大好きだから、作り方を教えて」と、大人になってからおっしゃったそうなんです。そしたらお母様が「何言ってんの、あれはコープのちゃんぽんよ」って。落語の枕みたいですけど、本当の話です(笑)。
それを見たとき、ちゃんぽんのリニューアルで大事にすべきは「手作り感」だと。キンレイの営業担当の方からも、おうちで作るような手作り感を持たせながら、誰がいつ作っても必ずおいしくできるという部分をしっかり守ってリニューアルしましょう、とご提案いただいていて。すとんと腑に落ちた感じでした。
澤田
2023年、藤田さんがご担当になられて2回目のリニューアルをしたときですね。
藤田
すごく細かい部分で手作り感を出していただきました。野菜の量を増やしてほしいという「組声」を活かしつつ、よりおいしくするための手間ひまをじっくりとかけてくださって。
澤田
野菜の甘みや旨みを引き出すことはちゃんぽんの最重要課題のひとつなので、単純に量を増やすだけでなく、さまざまな工夫を重ねました。2017年には炒め野菜をおいしくするための巨大な鉄鍋を特注しましたし、2023年には一部の冷凍野菜をやめて、すべて生野菜に切り替えました。鉄鍋は思い切った導入でしたが、味も売上も劇的に向上しましたね。
藤田
どう考えても、ステンレスの方が扱いやすいんです。焦げ付きにくいし、手入れの楽さは比較にならない。でも「熱伝導のよい鉄のほうが野菜の食感や風味を引き出せておいしいから」と、そのためにわざわざ巨大な鉄鍋を特注された。そこまでこだわるメーカーさん、なかなかないですよ(笑)。
炒め方も細かく決まっています。キャベツは芯の方が甘みが出る、でも炒め時間はかかる。そこを計算して、まず下半分、その後で上半分。家庭だったら1個を半分に切るだけですが、ものすごい量を下処理して、さらに上下にわける。で、下から順に炒めていく…キンレイさんの製造工程は、こういったこだわりの積み重ねですよね。
澤田
何かしらの改良をする際、普通ならその改善点1つだけで終わるところですが、「どうせやるなら、よりおいしくしたいよね」というのが根本にあるので、結果的に細かいこだわりが積み重なっていくのかもしれません。
藤田
そうそう。「どうせならおいしくしたい」というのは、御社の営業・現場、どなたからもよく出てくる言葉です(笑)。
澤田
上下を時間差で炒めるというのは、「組声」がきっかけでした。「キャベツが苦い」という意見がけっこうあると伺いまして。キャベツって加熱不足になると、人によってはちょっとした苦味を感じます。感じない人のほうが多いかもしれませんが、実際にそういう声があるのならと。「組声」あってこそたどり着いた改善です。
藤田
リニューアルのタイミングはいろいろありますが、何にしろまずは組合員さんの声を振り返って、解決すべき課題がどこにあるかを探ります。それをキンレイの担当者にお伝えすると、真摯に取り組んで、必ず最良の落としどころを探ってくださる。この信頼感は本当に大きいです。
「CO・OP長崎風ちゃんぽん」は、いつも冷凍庫にあって、「今日の夕飯どうしようかな」っていう時にすぐ使えて、しかもそれが長く続いても飽きない、という存在であってほしいんです。パンチのあるものは一口目はおいしいですが、「毎日食べたらどうか」「こどもや高齢者ならどうか」「スープまで飲み干すならどういう味がおいしいか」「おうちで具材を足したい組合員にも寄り添えているか」というのも考えていくのが、コープ商品の在り方です。
澤田
組合員のみなさまと触れあう機会も設けておられますよね。うちも学習会で試食していただいたり、工場見学に来ていただいたり。おかげで私たちも「いろんな地域の麺があるから次はうちの地域を出してよ」などの声を直接聞けたりして、とてもいい場をいただいています。

コープ商品で監修商品? 反対の声を歓喜に変えた「熱」
澤田
コープ商品で監修麺を初めて実現させたのも藤田さんの推進力と想いの賜物です。結果的に大ヒットとなった「けやき監修 札幌味噌ラーメン」ですが、最初は、「なんでコープ商品が監修品をやる必要があるのか?」と反発も強かったですよね。
藤田
本来、コープ商品は「誰もが食べられて、誰もがおいしい」「毎日食べても飽きない」という、スーパースタンダードをまず組み立てる必要があります。今までもこの先も、それは変わりません。その中で、私はずっと監修麺をやりたいと言い続けていたんです。
世間的にはすでにさまざまな監修麺が出ていて、「時流に乗るのか?」という指摘もありました。でも、当時はまだコロナ禍で自由にお出かけできない状況。組合員さんはシニアの方が多いので、旅行どころか買い物にも出にくい、だから宅配をという方も多かったんです。「旅気分を味わえるご当地麺、できれば監修がついて、本当にその店に行ったようなワクワク感が味わえるものを食べていただきたい」という想いを、かなり熱量をこめてあちこちで語りました。
澤田
元々広報の方なので、伝えるポイントや言葉の組み立て方を熟知しているというのはありますが、とにかく熱が伝わってきますよね。藤田さんのこの熱がなかったら、コープの監修麺はなかなか実現しなかったと思います。ちなみに札幌のけやきを選んだ理由は何ですか?
藤田
監修麺を出したいとひとりで言い続けても意味がないので、各エリアの生協さんに「どこの、どの味がいいですか?」と聞き取りをしながら、一緒にやりましょう!と巻き込んでいきました。で、第1弾は札幌の味噌ラーメンで!と。中でも「けやき」に決めたのは、私自身が大好きというのはもちろんですが、当時、冷凍具付き麺のカテゴリではほかで監修をされていないのも大きかったです。コープでしか食べられないもので組合員さんに喜んでほしかったので。
澤田
商品設計において、ちぢれ麺が大きな課題でした。
藤田
当時はまだ御社でもちぢれ麺は出されてなくて、手探りの状態から。でも実際に店主さまとやり取りをしていただいたら、第一次試作のレベルが高すぎて、「これができるならもっとここまではいけますよね」とハードルがさらに上がってしまいました。
澤田
キンレイあるあるですね。(笑)
藤田
先々はほかの商品でも使う目算があったにしろ、形としてはコープ商品のためにちぢれ麺の工程を確立していただいた、と言っていいんでしょうか?
澤田
そうですね。じつは、ちぢれ麺は前々から作りたくて、チャレンジはしていたんです。でも失敗続きで、保留になっていた。できてみれば簡単ですが、それまでは試行錯誤の連続ですから。監修店さんに「ちぢれじゃないと出せない」という強い意向がありましたし、藤田さんの想いも非常に強かったので(笑)、これはやるしかないぞと。なので、もしあのときの「けやき」がなかったら、ちぢれ麺の完成はその先何年も遅れていたと思います。
藤田
確かに、機械があればできるという簡単なことではありませんよね。私も立ち会いましたが、本当に工場長以下総出で、細かい試行錯誤をされていて。私は何もできないので見ているだけですが、みなさんの真剣さと想いは忘れられないですね。
澤田
ありがたいことに、発売後の組合員さんの反響も良かったんですよね。
藤田
はい、とても。「旅行ができない中で、こんな本格的な札幌味噌ラーメンが食べられて、しかも「けやき」に行ったような気持ちになれる!」という、意図した通りのお声をいただいて。本当に嬉しかったです。
澤田
発売前には、会員生協の方たちから「日本生協連の商品担当の人、尋常じゃない熱量でけやきのことを喋ってはるで」という声も耳にしました(笑)。
藤田
推し活ですね(笑)。

工場の「長いレシピ」に象徴される、ものづくりの姿勢
藤田
いろんな冷凍麺がある中でキンレイさんの商品はなぜこんなにおいしいんだろう?と考えてみると、たとえば「1メニューに1麺」というところ。「CO・OP長崎風ちゃんぽん」なら「CO・OP長崎風ちゃんぽん」のための麺をまず決めます。でも、こだわるのはもちろん麺だけではなく、具材もスープも、全体でおいしくなるようにトータルで設計する。だからこそ最終的に1つひとつがおいしくなっていくんだなと。
これ、一般消費者として「おいしいな〜」と食べていたときには全く気付いてないですよ。でも担当になってやり取りをする中で、「おいしくなる理由」がちゃんとあるんだと思いました。
工場で使うレシピがものすご〜く長いのも特徴ですよね。
澤田
工程ごとのチェック表ですね。確かに、かなり長いです。まず開発チームが相当な時間をかけて「この味、この方向」と決めますが、それを工場のラインに落とし込む際には改めてさまざまな調整が必要になります。いざラインにのせてからも改善は必須ですし、細かく細かく決めておかないと、「この味、この方向」がぶれちゃう。だから、工程表はどうしても長くなるんです。
藤田
調理は、すべてこのレシピ通りに進みます。衛生上の問題や味のブレがないように、言ってみれば「工業製品」として成り立つような完璧な仕組みで動いているんです。でも実際の現場を見ていると、「製造」ではなく「調理」。緻密に組み立てられたレシピがまずある、でもそこに人の手や想いが組み合わさっているからこそ、あの手作り感が出るんだと思います。
人の手で作った温かみのある味わい。開発も営業も製造現場も一丸となってそこにこだわっておられるから、「キンレイはおいしい」という結果になるのかなと。
澤田
ありがたいお言葉です。新商品やリニューアル品の工場の初回点検で細かくチェックされるのも藤田さんたちのお仕事ですが、工場のスタッフとしては「日本生協連さんの点検がある」ということで普段以上にピリッとします。しかも藤田さんはオブラートに包まずにピシッと言う人ですから(笑)。それが改善のきっかけになって、より良い在り方が保たれると思っています。
藤田
私としては、現場で学ばせてもらうことが本当に多くて。スパイスひとつ取っても、最終的に際立たせたいのは辛みなのか、香りなのか、うま辛なのか。ひとつずつ深掘りして、「じゃあこういう方法があります」というのを具体的に共有しながら進めてくださるので、そのやりとり自体が非常に勉強になりました。
目線合わせも独特です。商品の到達点を探るために数値的な話もされますが、「このお店のこのメニュー」という合わせ方もされる。開発の方も営業の方もあちこち食べに行かれてますし、もちろん私も行ってます。「その中でどれがおいしいと思いました?どれがコープ商品にふさわしいですか?」という目線合わせができるので、試作が進めやすいんです。
ついつい長くなっちゃいますが、これでも選りすぐってます。私、工場の話だけでも4時間はしゃべれますから(笑)。
澤田
ありがとうございます(笑)。目線合わせは本当に重要なんです。最初の段階でちゃんと目標設定をしておかないと、後々ぶれてしまいますので。「こういう味を作りましょう」という具体的な目標点があれば、途中でいろんな調整をしても「目指していたのはここ」と戻りやすいですよね。
近い将来、さらに先の未来を見据えながら、これからも共に……
藤田
私は当時、若輩者のくせに相当バンバン言ったと思いますが、異動の話をお伝えしたとき、大阪工場の方が「藤田さん、どうやったら麺の担当に戻ってこれますか」と言ってくださって。「私が教えてほしいです〜」って泣きながらお答えしました(笑)。すっごい嬉しかったです。
澤田
担当されたのは2年ちょっとでしたから、振り返ると短かったですよね。でも、その後も監修麺は第2弾、3弾と続いて、そのきっかけを作ったのは藤田さんですから。コープ商品に監修店をつけること自体が簡単じゃない中で、後に続く突破口を作っていただいたと思っています。
藤田
私にできたことは多くないです。キンレイさんからいつも私どもにご提案いただくのは「3年後はどうしましょうか?」ということです。みなさん食に対する造詣が深く、「今売れているもの」「今守るべきスタンダード」への感度も高い。でも同時に、3年後はどこに行こうかというのをいつも一緒に考えてくださるのが、本当にありがたいなと思っています。
澤田
日本生協連さんとキンレイがパートナーとして長年ご一緒してきたという自負と、「聞いていただける」という信頼がありますから。ものづくりって、完成までに少なくとも半年から1年、長いものだと1〜2年かかります。今動かないと1年、2年、3年後が進んでいかない。でも、信頼関係がなければ、目の前の課題に終始して、先の話をしてもなかなか聞いてもらえません。
「来年これを出すから、その次はこれですね」といった先々の話ができて目指すところに共感し合える関係性なら「そこに向けて一緒に進みましょう!」となるので、より良い結果が出せますよね。
藤田
飲食店は口コミなどを見てふらっと食べに来てくれるお客様がいますが、冷凍麺は買って食べないと味が分かりません。ましてやコープ商品はコープのお店や宅配でしか買えないので、どうやって今のファンを守っていくか、新しいファンを獲得していくかは大きな課題です。先のことを見据えた話ができることは本当に価値があります。澤田さんとしては、この先どうなっていたいという目標はありますか?
澤田
そうですね、キンレイがおいしさを追求するのは当たり前で、そのこだわりは大事にしていきますが、それをお客様に押しつけたくないという想いもあります。単純に「おいしいな」「家でもこんなにおいしいものが気軽に食べられて幸せだな」と思っていただきたい。それは、常に目指していたいです。そして私たちの企業活動は利益だけを追い求めるのではなく、「みなさまの役に立ちたい」という想いを常に大切にしているので、10年、20年、100年後にでも、冷凍麺や麺業界の発展、日本の食文化育成に少しでも貢献できるような会社になっていたいと思います。

関連リンク
関連記事

発見 05

ふわっととけるワンタンめん、心に残る一杯を。
カドヤ食堂・橘和良さんの飽くなき探究心と真摯に向き合い、キンレイ渾身のワンタンめんがついに完成。開発担当・齊藤と橘さんの対話から、「本物のおいしさとは何か」を紐解きます。

発見 06

飯田商店と挑んだ、最高峰の一杯。
この一杯で幸福を届けたい──「最高峰のラーメン」と称される飯田商店のおいしさをプレミアムな冷凍麺に。若手ふたりを中心とした開発部の飽くなき探究心、その結末とは……

発見 13

変わらない風景をつくる、一杯の鍋焼うどん。
冷凍食品にそこまでやる?キンレイの常識は、業界の非常識。でも、妥協しないからこそのおいしさがあると私たちは知っています。冷凍の鍋焼うどんをめぐる、熱い物語です。