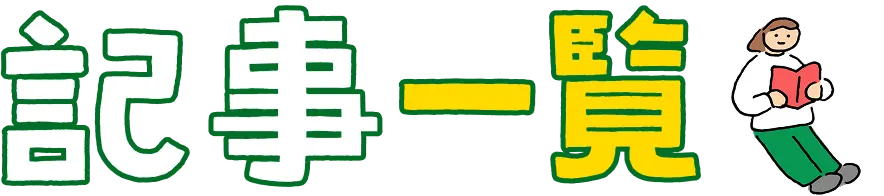はじまりは恩送り。
四海樓ちゃんぽんの126年。
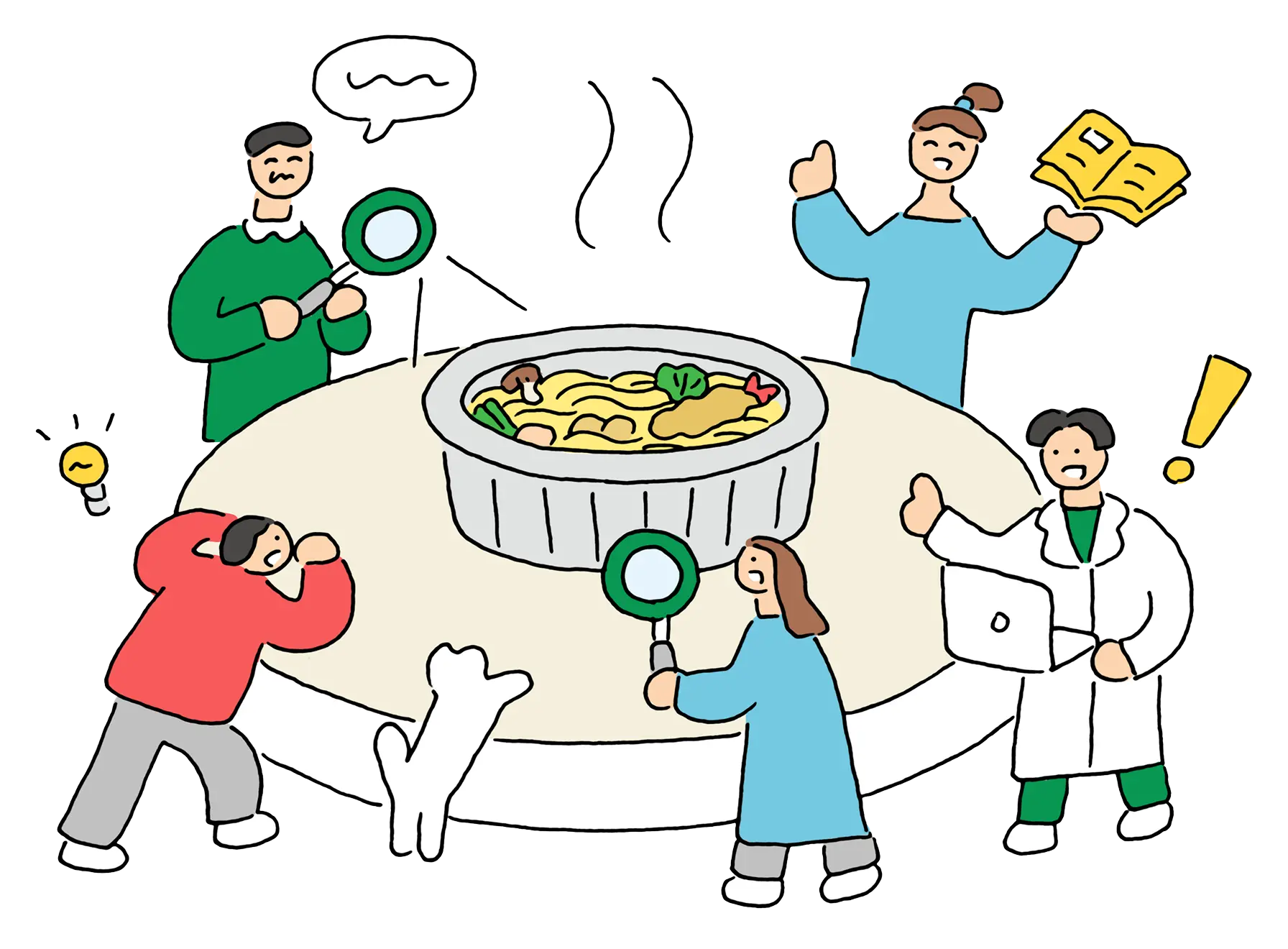
発見 22

ちゃんぽんは単なる料理ではなく、理念を具現化したもの。そう語るのは発祥店「四海樓」の陳優継さん。126年の歴史と込められた想いを伺いながら、キンレイのロングセラー開発秘話に迫ります。

中華料理「四海樓」・陳優継
ちゃんぽん・皿うどん発祥の店「四海樓」の四代目。長崎市に生まれ、東京の大学を卒業後、銀行勤務を経て代表取締役社長に就任。華僑文化や長崎の観光振興にも尽力している。

キンレイ営業本部(企画部)・大倉
育ちは京都、社会に出てからは東京・奈良などで暮らしてきました。旅先で器やアンティークを物色するのが趣味。2児の父。4歳の長女は「お水がいらない 四海樓」ヘビーユーザーです。
始まりは「恩送り」──ちゃんぽんは、こうして誕生した
大倉
魚介のダシが効いた濃厚なスープ、味のしみこんだ太麺、たっぷりのキャベツにイカやエビ──これぞ「ちゃんぽん」という味わいを、先ほどお店でいただきまして。体にしみわたるようなおいしさを堪能しました。
今や長崎名物として全国に知られるちゃんぽんですが、発祥の店としてこの料理をどのように考えておられますか?
陳さん(以下敬称略)
料理そのものとしての定義でいえば、私のひいおじいさん・陳平順の出身地である福建省の料理をルーツにしていますが、決まった形があったわけではありません。100年以上前なので、四季のものをまさに地産地消していた時代。キャベツやエビ、イカなど長崎で採れる海の幸・山の幸を活かし、栄養のバランスも考えながら、少しずつ今の形ができてきました。
しかし実際のところ、私たちにとってちゃんぽんは単なる料理ではありません。恩送り、英語で言うところのPay it forwardという理念が込められています。曾祖父は家族が多く、中国で食べ物に苦労した経験を持っています。19歳で独立して長崎にたどり着いたわけですが、自身が苦労した経験から、当時の留学生や華僑同胞のために「おいしくて栄養価が高く、安価なメニューを」という想いで作ったのがちゃんぽんなのです。
大倉
お腹を満たすだけでなく、明日を生きる力になる一杯を届けたい。そんな想いがあったからこそ、100年以上続く文化になったのだと思います。名前の由来も、よく言われる「まぜこぜ」ではないそうですね。
陳
間違いではありませんが、原点ではないんです。そもそもは、長崎の華僑の間で交わされていた挨拶言葉からきています。「ご飯を食べる」を意味する福建の方言──セポン、シャポンなど発音は地域によって違いますが、語尾を上げると「お腹すいた?」「ご飯食べた?」という意味になる。それが「ちゃんぽん」の語源になったと言われています。
大倉
互いを気遣う気持ちや恩送りの想いが出発点だからこそ、商標を取ることもされず、長崎のみなさんに広めていかれたんですね。
陳
「日本中の人が喜んでちゃんぽんを食べてくれたら、それで満足だ」と考えていたようです。今でもその考えは変わっていません。実際、長崎のお母さんたちは冷蔵庫の残り物で思い思いのちゃんぽんを作り、日常的に食べてるんですよ。ご当地名物というのは、そんな風に地元民に浸透しています。そうでないと、本物の名物として定着しないと私は思っています。

食文化への想いが共鳴した、「お水がいらない」ちゃんぽん
大倉
キンレイの『四海樓ちゃんぽん』は「お水がいらない」シリーズの中でも代表的なロングセラーですが、四海樓さんにはその前から監修をお願いしています。当初、伝統あるちゃんぽんを冷凍で出すことに抵抗はなかったのでしょうか?
陳
長崎で126年の歴史というのはまだまだひよっこ(笑)。カステラなんて400年ですから、我々には「老舗感」がないんですよ。だからこそチャレンジしやすい環境があります。キンレイさんとはアルミ鍋のちゃんぽんで初めてご一緒しましたが、大きなチャレンジでしたね。
我々はレストランとしての経験しかないので、別の形態で提供するとなれば、根本から考えないといけない。その考え方を模索することからして、すでにチャレンジでした。
大倉
具体的にどういった考え方で臨まれたのでしょうか?
陳
お店と同じ味にできれば一番ですが、冷凍して保存するので、店と同じ味にはなり得ない。仮にできたら困るのはウチだよね、というのもあります(笑)。
開発当初は「どこまでの近似値でよしとするか」を考えていましたが、九州の方たちは「ちゃんぽんはこういう味」とご存知でも、それ以外の地域ではそもそもちゃんぽん自体がまだ知られていなかった。うちの味に似ているかどうかより「おいしいな、これは何?」と、まず知ってもらいたいと思いました。
大倉
「お水がいらない」シリーズで監修をお願いしたのは、最初のアルミ鍋からしばらく経っていましたよね。
陳
「お水がいらない」シリーズが出たときは衝撃を受けたんですよ。よくぞ開発されたなと感心しました。
僕は東日本大震災で炊き出しに伺っていて、水の貴重さを痛感した経験があります。現場に行ったのは3週間後でしたが、それまで被災地では温かいものを食べられない人も多かった。カセットコンロだけで調理が完結したらいいな、と強く思いました。
それからしばらくして、「お水がいらない」の商品を『マツコの知らない世界』で見まして「これをちゃんぽんで作れたら最高!」と思ったんです。翌日、従業員の何人かが「社長、昨日の番組見ました? あれをちゃんぽんでやったら…」と言ってきまして。「やっぱりそう思った?」と盛り上がりました。その1〜2か月後にキンレイさんからお電話をいただいて「待ってました」の気持ちでしたよ。ご縁を感じました。
大倉
あれは私たちとしても非常に嬉しい流れでした。ちゃんぽんはラーメンのように丼でできあがるのではなく、鍋の中で煮込んで仕上げる料理なので、キンレイの冷凍麺と共通する部分が大きいというところもありますよね。
陳
長崎華僑の表現では、ちゃんぽんは「作る」ではなく「炊く」といいます。煮込み料理ですよね。キンレイさんの商品も煮込んで仕上げておられるので、非常に相性がよいと思います。
大倉
実は、キンレイの代表商品である鍋焼うどんの「鍋焼」にも「炊く、煮込む」という意味があります。奇しくも、煮込みながら素材の旨味を引き出すというちゃんぽんの考え方と同じです。ダシをいかにうまく取るかだけでなく、具材からも旨味が出て、最終的においしいものが出来上がる。もちろん、冷凍とレストランでは工程も味わいも違いますが、根本の「おいしさの作り方」には、光栄にも共通するものがあったんだろうと感じます。

作り方も想いも学ぶことで、キンレイの「四海樓らしさ」を表現
大倉
「お水がいらない」の開発では、どんなことを大切にされていましたか?
陳
同じ時期に出たお水がいらないシリーズにはラーメン店「横綱」さんの商品もあります。そこと比較しても「おいしい」と言ってもらえるもの、ラーメンと比べて「ちゃんぽんは違うおいしさだね」と思ってもらえるもの。それが第一条件でした。
大倉
様々なアドバイスをいただきましたが、大きな決め手のひとつは野菜をソテーする工程でした。
陳
「うちは鉄鍋で野菜をソテーしている」という話はしていました。で、岸和田工場のオープンイベントに伺ってみたら、鉄鍋を導入されていたんですよね。最初は「大丈夫ですか?」と心配になりました(笑)。この商品が長く続けばいいですが、もしコケたら無駄になりますから。でもそのとき、キンレイさんの覚悟を感じたのも事実です。
大倉
鉄鍋を使う意味を教わったうえで、社内で検討を重ね、ちゃんぽんの味に直結する必要な投資と考えての決断でした。
陳
現場でもお伝えしたんですが、香りが特徴的でした。工場に入ると、普通は工場の匂いがします。でもキンレイさんの場合は厨房と同じ匂いがしたんです。鉄鍋で香ばしく炒めているからこその香り。鉄鍋は扱うのもメンテナンスも大変です。でも間違いなく、味に直結する。味を作るのは口に入る調味料や材料だけじゃない。道具や工程でもおいしさが表現できることを改めて実感しました。
大倉
開発部の人間は何度も長崎に伺って厨房で作り方を見せていただきました。スープも何度か送っていただき、冷凍でできうる限りのおいしさ、四海樓らしさを出したいと試作を重ねまして、開発には1年以上かかりました。
陳
なかなかOKを出さなかったのは、キンレイさんならできる、という期待があったからです。できないと思ったら途中でやめてますよ。私自身「お水がいらない」の技術でどこまでいけるかという期待感が大きかったし、ちゃんぽんの可能性を広げたいというワクワク感もありました。
大倉
先ほど「同じ味を目指すのではなく近似値を探る」というお話がありましたが、実際に味や具材など柔軟にアドバイスをくださった印象があります。ちゃんぽんの元祖として守らないといけないラインはどのように考えておられるのでしょうか。
陳
たとえば四海樓でお出しするちゃんぽんには、にんじんは入っていません。でも別の形態を考えたとき「彩りがあったほうが売れます」という事情があるのなら、入れてもいいんじゃない?と僕は思っています。味が変わるような変化は困りますが、にんじんが入ってもおいしいですから。
あの価格で、手軽においしく味わえる冷凍ちゃんぽんがある。近似値のおいしさが出せるならそれだけで十分。仮にフルスペックで同じものを食べたいということであれば、どうぞお店に来てください、というシンプルな話なんですよ。
大倉
実際の開発では、最後に「イカの風味が足りない」という具体的な改善ポイントも示してくださいました。
陳
いわゆる「海鮮味」です。ちゃんぽんにはこの風味が欠かせないんですが、海鮮味といってもホタテやエビなどいろいろあります。エビの風味とかは僕も大好きですけれど、ちゃんぽんのあの旨みはイカなんです。そういう細かいところまで調整いただいて、ついに完成!という感じでしたね。

おいしいのは当たり前。ハマるちゃんぽんに出会ってほしい
大倉
私たちは50周年を迎えるにあたって、あらためて「キンレイのおいしさ・魅力とは何だろう」というのを考えています。陳さんにとって、「おいしさ」とはどんなものなのでしょうか?
陳
僕は「おいしい」というのは当たり前だと思っています。キンレイさん以外にも、冷凍、カップ、レンジアップなどいろんな企画をいただきます。ご一緒するかどうかを決める際においしさは最低限の条件で、その先にある関係性や考え方の一致こそが大事。お互いの考えが合うからこそ、こうして一緒にものづくりができているんだと思います。
おいしさという意味でいうと、僕にはもう一つ基準があって、それは「ハマるか、ハマらないか」です。長崎新地中華街にもいろんな店がありますが、まずいものを出そうとする店なんてありません。それでも「口に合わない」ということはある。ワインもそうでしょう。「この年のワインはまずい」ではなく、「自分の好みに合うかどうか」。それと同じです。
大倉
最近は新しいタイプのちゃんぽんも話題ですが、陳さんから見て「ちゃんぽんとしての許容範囲」のようなものは?
陳
ちゃんぽんで「まちおこし」をする自治体も増えていますし、魚介を使わずにおいしくするとか、ご当地食材を活かすなどのバリエーションがあっても問題ないと思います。明らかにちゃんぽんと違う食べ方が、あたかも定番のように広まってしまうのは困りますが、どのお店もこだわってオンリーワンのちゃんぽんを出している。「あなたがハマるちゃんぽんを探してみてください」というのが僕の考えです。
ただ、我々自身は四海樓の味を、ブレさせないことを常に重視しています。「なんとなく、この味」ではなく、明確に言語化・数値化することを心がけていますし、調理場のスタッフにも「お客様から『味が薄いとか濃い』と言われても、それに合わせて性急に味を変えないこと。ご意見は真摯に承るけれど、自分が規定通りに四海樓の味を出せているかを、確認する機会にしてほしい」と伝えています。そうでないと、どんどん味がブレますから。
大倉
味の守り方として、少数意見には影響されないとしても、大きなトレンドや時代の流れに合わせてレシピを変える、ということは?
陳
ないですね。というのも、食材自体が年々おいしくなっているんです。今のキャベツはそのまま食べても、昔より甘くておいしい。味というのは調味料だけで作られるわけではありません。だから作り方やレシピは変えずに、素材の力を引き出すことを大事にしています。
伝統は「守る」よりも「育てる」もの。過去も今も、これからも
大倉
祭事や食文化など、長崎に根付いたアイデンティティをとても大事にされていますが、それは意識して文化を担おうとしてきた結果なのでしょうか、それとも自然な流れだったのですか?
陳
文化や継承というのは、「今からやります」と意図して始めるものではないと思います。生活に根付いた習慣や地域ごとの風習がまずあって、小さい頃から当たり前のようにやってきたことが土台になる。意味がわからなくても、まずは続ける。その中で「これは何だろう?」と自分から疑問を持てれば、そこから次の段階へ進めるんです。疑問を持たずに終わる人もいますが、それも構いません。
僕の考えでは、伝統は「守るもの」ではなく「育てるもの」。守るだけでは衰退します。先ほどもお話ししましたが、できるだけ数値化・言語化することが重要です。そうやって具体的にしていくことでより多くの人と考えを共有し、次につなげることができると思っています。
大倉
晴らしいお話をありがとうございます。私たちキンレイは、ものづくりの現場で何を大事にするべきかを常に模索して、その中で「おいしさを表現するには、食材や土地の文化についても深く知る必要がある」という姿勢を一貫して大切にしてきました。
陳
僕が共鳴しているのは、まさにその部分です。「どういう想いで作っているか」を共有できるかどうか。それが一致していなければ、一緒にやる意味がないと思います。キンレイさんとは、そこが合っている。だからこそ、これまでやってこられたし、これからもきっといいものを一緒に作り続けられると信じています。
大倉
そう言っていただけると、とても嬉しいです。キンレイは、商品開発するときにまず、現地の飲食店や博物館を訪れ、歴史や地域性を含めて、食文化を理解することから始めます。
提供しているものから見ると冷凍食品メーカーでしかないのですが、一方で、メニューや味、素材選定など商品企画・開発をしていくなかで、我々の届ける「おいしさ」の根本は、日本各地で紡がれてきた食文化によって支えられているとひしひし感じます。
だからこそ、我々自身も享受するだけでなく、食文化が更に発展していくために社会的な責任と役割を積極的に担っていきたいです。
今回は、たくさんお話を聞かせていただき、ありがとうございます。今後も様々なことをご教示いただきながら、ご一緒させていただけると嬉しいです。

店舗情報

中華料理 四海樓
-
四海樓は、明治32年創業の老舗中華料理店で、長崎ちゃんぽん・皿うどん発祥の店として知られています。創業者・陳平順が考案したちゃんぽんは、栄養とボリュームに優れた庶民の味として、今では長崎の食文化を代表する料理として全国に広がり、多くの人々に親しまれています。
関連リンク
関連記事

発見 03

理念と技術が結ぶご縁。四海樓店主 陳優継
名店たちが語る、キンレイとの想い──。 四海樓から50周年を祝うメッセージをいただきました。

発見 05

ふわっととけるワンタンめん、心に残る一杯を。
カドヤ食堂・橘和良さんの飽くなき探究心と真摯に向き合い、キンレイ渾身のワンタンめんがついに完成。開発担当・齊藤と橘さんの対話から、「本物のおいしさとは何か」を紐解きます。

発見 06

飯田商店と挑んだ、最高峰の一杯。
この一杯で幸福を届けたい──「最高峰のラーメン」と称される飯田商店のおいしさをプレミアムな冷凍麺に。若手ふたりを中心とした開発部の飽くなき探究心、その結末とは……